昨日私は、昨日のサンフレッチェの戴冠は1969年天皇杯決勝以来の国立での戴冠と書いた。いろいろデータを洗ったつもりだったのだが、肝心の3年前のルヴァンカップ決勝戦を見落としていた。御指摘いただいたとおりあれは国立競技場である。よって、あのときに呪縛は解いていたのだ。ピエロスのPKと美しいシュートで。まったくお恥ずかしい限りなのだが、旅先で寝ぼけ眼で書いたからということで御寛恕願いたい。
そうかと思うと、今日はラグビー慶明戦で「思い込み」による悲劇的な幕切れがあった。後半追い上げた慶應だが、キャプテンがラストプレーで負けていたにもかかわらずタッチに蹴り出してしまったのだ。プレイを継続していれば、ひょっとして勝てていたかもしれない点差であっただけに、本人は責任を背負い込んでいるだろう。救われるのはまだ対抗戦だったことで、大学選手権だったら泣くに泣けないところだった。
ことほどさように、思い込みというのは恐ろしい。下手に自分は知っていると思うところに現れて逆の知識をもたらすから、怖いのだ。私の専門分野でもそうで、通説的見解と思い込んでいたものが実は違っていたり、果ては法改正を見落として旧法実務の見解にとらわれたりと言うことだってあるのだ。だから、リサーチは大事だし、そのアビリティがないと無能も同然なのだ。
話は変わるが、カープも秋季キャンプが始まったようで、昨日のサンブレの戴冠のニュースの裏でこっそりといくつかでていたが、その中に斉藤優汰の動向があった。なんでも動作解析の指摘を受けて指にかかるボールを投げられるようにするとのことである。しかし、こんなのを任される黒田博樹も不憫でならない。
本人も置かれている立場は理解できているようで、これで結果を出せなければあとはないなどと殊勝に言っているが、はっきり言って3年もたった今やることがという気がする。どう好意的に見ても1年遅い。あるいはルーキーイヤーの終盤に少し結果が出かけたのでできると思い込んでしまったのか。まあ私も過剰な夢を見た節があるので大きな事は言えないが、これも一種の「思い込み」なのかもしれない。
反対に一番不安なのは常廣羽也斗である。はっきりいうが、誰も彼に何も言えないのかという気がする。彼については、卒業を諦めろという一言に尽きる。なんでも上本崇司も明治大学を4年ダブって(すなわちカープのユニフォームを着た状態で)卒業したようだが、常廣と上本とでは置かれている立場が違うのだ。
聞き及んだところによると、常廣は野村祐輔塾を早々にドロップアウトしたらしい。髙太一や辻大雅を覚醒させた手腕にあずかるのを拒否したも同然である。要するに、聞く耳持てないタイプなのではないか。そりゃ結果出せていたらそれで良い。しかし、カスほどの結果も出せていない中で聞く耳持てず、しかも二兎を追おうなんて、虫が良すぎるにもほどがある。
まあ、これも「自分はできる」という一種の思い込みなのかもしれない。彼らの場合は、結果が出せなきゃ淘汰されるだけだから良い。少なくとも自分は、そうならないように肝に銘じたい。ましてや本業でそんなことやると、自分に不利益になるだけだ。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング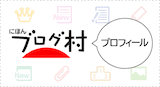
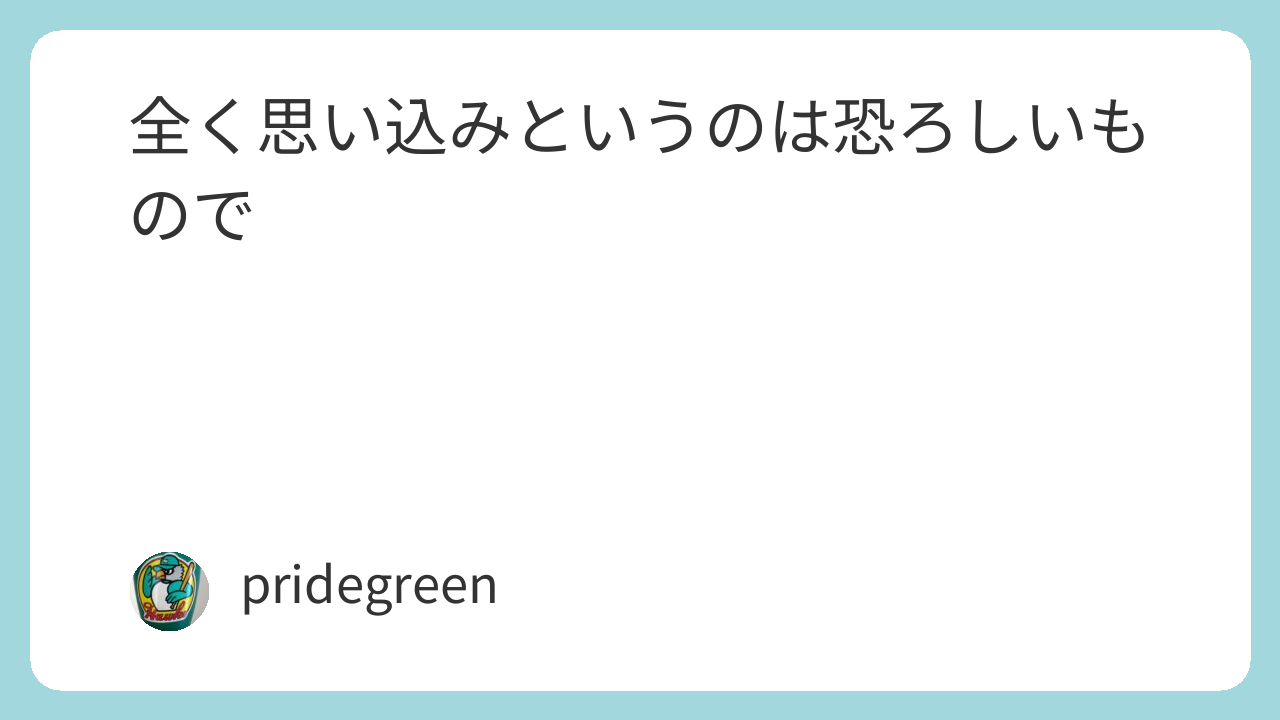
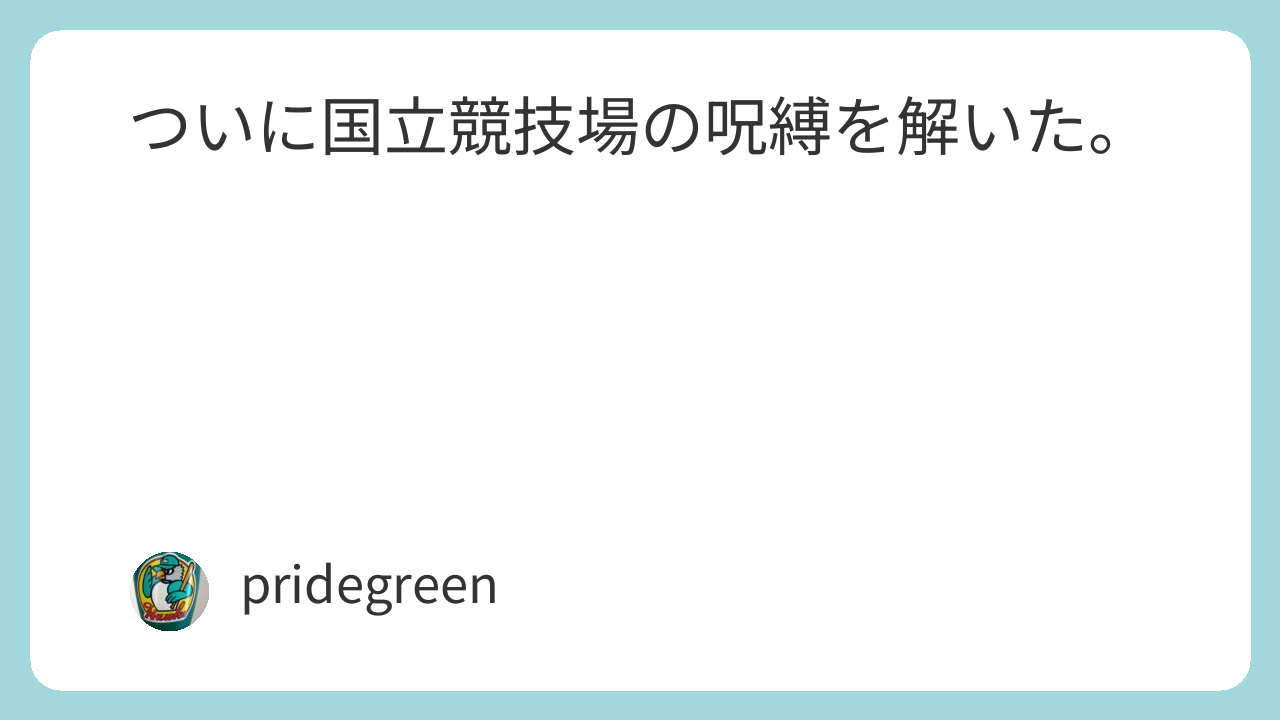
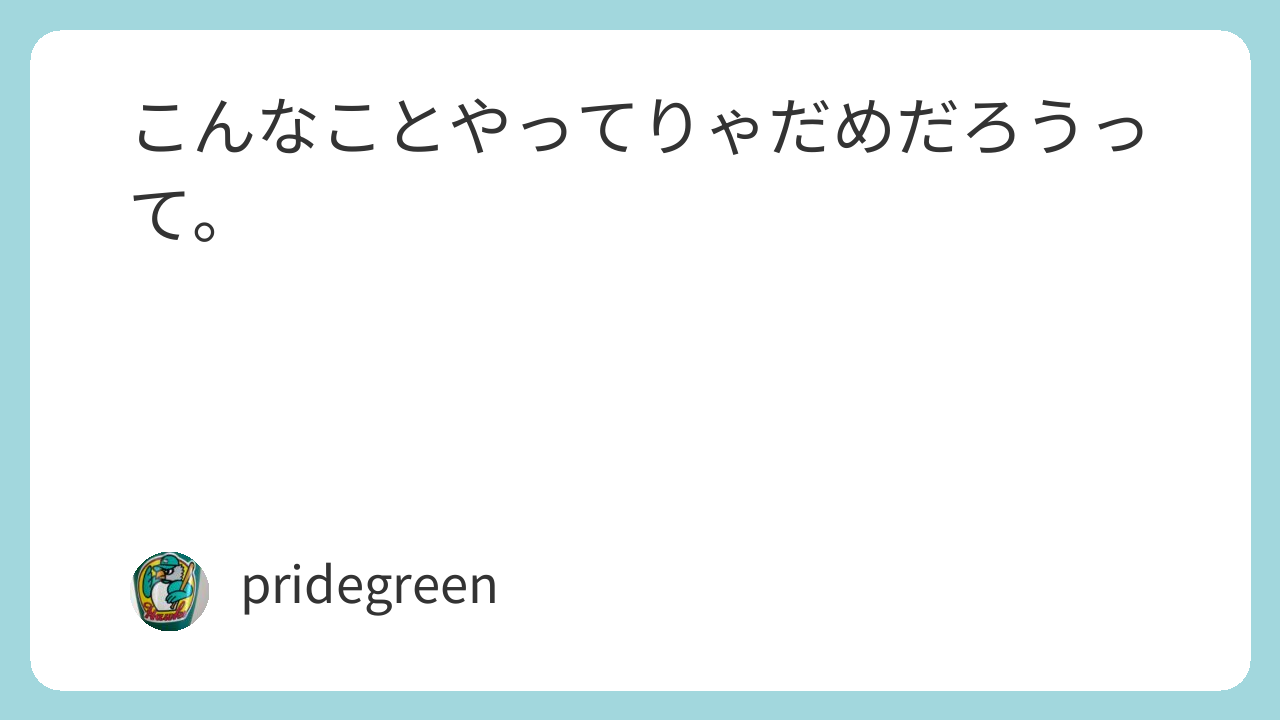
コメント
気になったんで書かせていただきます。
慶応明治の大学ラグビー最後のシーンは
思い込みではなくこのとき軽い脳震盪を起こしていた疑いがあります。
そもそもラグビーはゲーム中しっかり会話をしているので
あれだけの競り合いでスコアを間違えることはまずありません。
あと、再放送で確認しましたが
ボールを蹴り出した後鼻血が出ていたので
意識に何か問題があったのかもしれません。
まあ、対抗戦は去年の決勝が帝京対早稲田だったので5枠(3だが大学選手権決勝進出リーグ所属チーム枠が増えるため)
今年の慶応が早稲田や帝京に勝てるとは思えないので青学・立教・日体次第になりますが
大学選手権に向けては痛恨の1敗になってしまったので
救われることはないですね。
プロ野球みたいに、143試合もしませんのでね。
思い込みって、恐ろしいものですね。
「サンフレッチェの国立での戴冠は、肝心の3年前のルヴァンカップ決勝戦を見落としていた」状況は、「誤認」に近いかもしれません。データを洗い確認作業をしたうえでの認識の誤り。意図的に信じ込んだわけではなく検証の過程で漏れがあった、ということなら。。。「思い込み」は、検証されていない前提に基づく信念ですので。
哲学的には、「思い込み」と「誤認」は認識論(epistemology)の領域に属します。「悲願」「呪縛」「聖地」などの語彙は、定型化された語りの枠組みです。「国立の呪縛」が「記憶の錨」として機能していたとすれば、今回のケースは「思い込み」と「誤認」の境界或いは混在かもしれません。
それでも管理人さんは、まだまだ頭の中がクリアなほうなんじゃありませんか。俺の場合、映像記憶(“eidetic memory”or “photographic memory”)に依存し、楽譜を一度見ただけで暗譜できたり、板書を写す必要がなく最小限の学習量で学業成績が良かったり。。。しかし、映像記憶は永遠に続くわけではなく、18才くらいで弱まりその能力が衰えたとき、代替手段が分からないんです。何せ20才まで「意味記憶」「構造記憶」「物語記憶」などの記憶法を駆使した経験が1度もなかったので。
ですので、勤め始めてから「思い込み」「誤認」「勘違い」を含めミスが急増しました。俺を含め職場の者は、空気を読めないKYのオタクばっかりなので、遠慮なく俺のミスを突いて「公開処刑」するんですね(笑)。普通の感覚の持ち主なら、「公開処刑」されると恥ずかしかったり屈辱的だと感じるようですが、俺の場合はミスを「公開処刑」されることで、正解を脳に刻む新たな記憶法をゲットできたので、ミスを人前で指摘する方には感謝しております。
また、外国語を習得するにあたり、ある程度の基本をインプットできれば、どんどんアウトプットしていったほうが身に付きます。現在、日本には外国人のコミュニティが増えているので、そういう場に出向きアウトプットしていけば、間違っていたら「公開処刑」されます(笑)。それで正解が脳に焼き付きます。
ところで、英国在留中は不運?にも友人はスコティッシュばっかりだったので、身に付いたのが”Scottish English”。で、本場スコティッシュの発音は訛がキツくてイングランド人でさえ、聞き取れないケースが多々あります。さらに、”Scottish English”は、Aye- Yes (はい) Dinnae- Don’t (〜しないで) Canny- Can’t (〜できない) Piece – Sandwich (サンドウィッチ) Tattie-Potato (じゃがいも) Ken-Know (知る) Greet-Cry (泣く) Dreich- Cold Wet Weather (寒くて湿った天気)等々、スラングのリストがどこまで行っても終わりがありません。最早、英語じゃーありません(笑)。
イギリスといっても、スコットランド人とイングランド人では民族のルーツが異なり、対立する「外国」的な関係で双方の相性は良くないです。スコティッシュイングリッシュはクイーンズイングリッシュに対するカウンターカルチャー的側面を持っています。
同国内の白人同士でさえ対立構造が潜んでいるのですから、移民と共存なんて出来るはずがありません。
いつものように、話が飛び飛び、雑文になってしまい、失礼しました。