はっきり言ってやるけど、今日の山野太一をむざむざ楽逃げさせてあろうことか勝ちまでプレゼントするようなチームに、クライマックスとか何とか言う権利は、ない。ただひとこと、アホかお前らはと言うのみだ。こんなクソみたいなオフェンスやってて、なにがAクラスか。冗談は野間の顔だけで十分や。
今日の敗因を、バカープファンはきっと高橋昂也に求めるだろうが、それなら早く替えればええやんというだけの話。確かに2回以降はボロボロだったが、それで3回のマウンドに上げた新井のセンスのなさにはあきれるほかない。結果的に、それが試合を決めてしまったのだから、ほんとうにアホな指揮官敵より怖いとはよく言ったものだ。
そもそもブルペンデーというのは、頭の良い指揮官がやって活きるのだ。どこで替えるか、誰をどう配置するかというのはなかなか難しい。そもそも、継投というのは勝負にとってはリスク要因のひとつでもあるのだ。それなのに、単に投手の並べ詰めしかできない下等霊長類には、どだい無理な話なのだ。
それと、モンテロは弱点見破られたね。インコースの速い球は結構しばくけれども、入ってくる球には脆い。今日は端的に言えばモンテロのせいで負けたのだから、打撃コーチは大反省して、モンテロときちんと会話の上修正しないといけないが、たかが小窪みたいなハナクソなんぞにそれができるかな。
それと、9回表。あれを見て、ああやっぱりカープは作戦までハジメの息が掛かってるんだろうなと思わなきゃだめだ。申し訳ないが、今の佐々木に星なんか打てない。まずはそこから代打を送るのが正着手だろうが、なぜか佐々木には代打も代走も守備固めも送られない。確かに試合の流れからしてどうでもいい場面では出しとけばいいが、戦略上重要な場面では別異の配慮が必要だろう。
で、その次に出した代打が野間。ほんまに、冗談の筋が悪すぎる。野間なんかにA級のピッチャーが打てるわけない。それなら神宮には異様に強い二俣のほうがよかったかもしれない。というより、本気でクライマックスとか何とか言うなら、こんな寸足らずは今二軍で打ち込ませておいて、勢いのある選手を入れたほうがましだ。
しかし、カープはやらない。というより、異様なまでに入れ替えが少ない。まして今のカープはチームの流動性を高めても良い時期である。なのにそうならないということは、やはりハジメの介入があると見たほうがよい。今の一軍メンバー、ことにオフェンスは、ハジメの希望枠でがんじがらめにされているというのが正しい。
ちなみに今日のウェスタン対ホークス戦、初回2点先制しながら、先発投手がすぐ吐き出し、そして大崩壊して敗れた。その大崩壊した主は斉藤優汰。言わずとしれたバリバリのハジメの希望枠である。似たような境遇に日髙暖己がいて、この2人の使い方はファームでも相当気が使われているようである。それを知ってか知らずか、この2人が投げるとオフェンスの援護に欠けているのは気のせいか。
明日は常廣羽也斗が投げるようだが、柳の下にそうそう2匹も3匹も泥鰌はいるものかと思う。しかし、相手先発は育成出身ルーキーのアンダーハンド下川隼佑。カープも安く見積もられたものだ。きっと両外国人は打てないだろうから、代役を考えなきゃいけないだろうが、そうなるとまたハジメにお伺い立てなきゃいけないのかね。あー莫迦莫迦しい。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング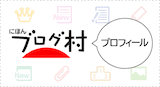
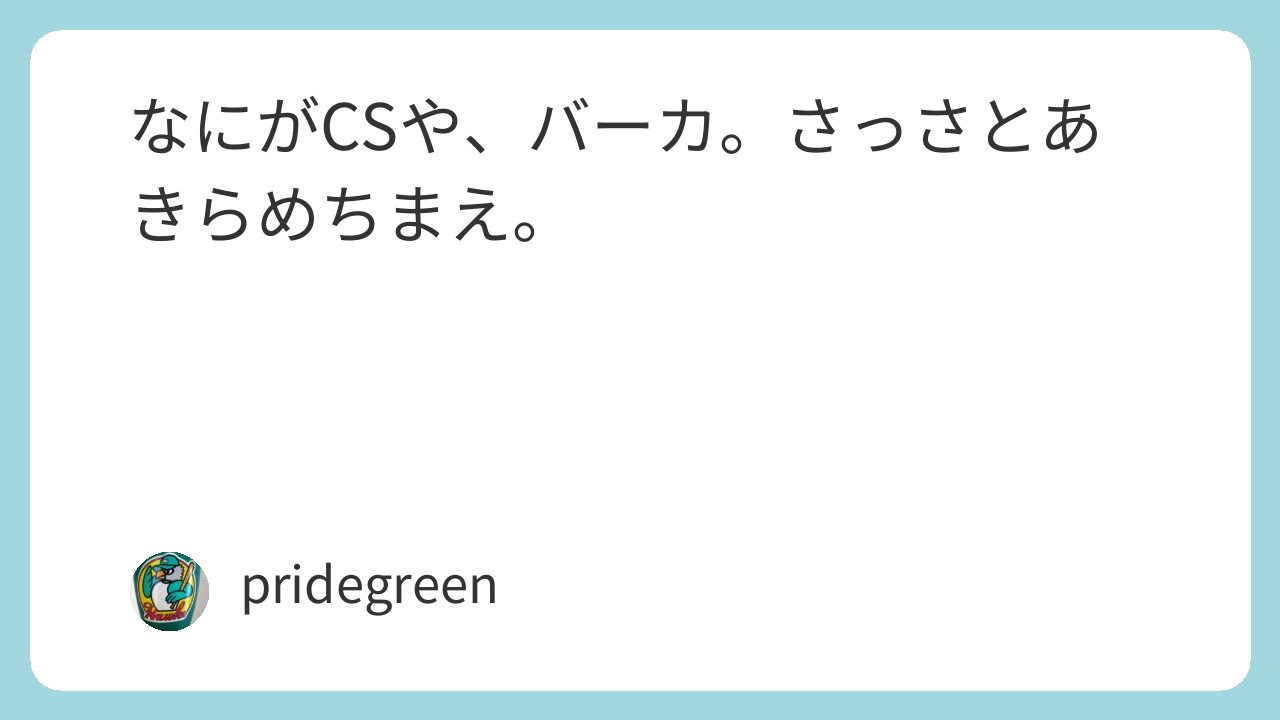
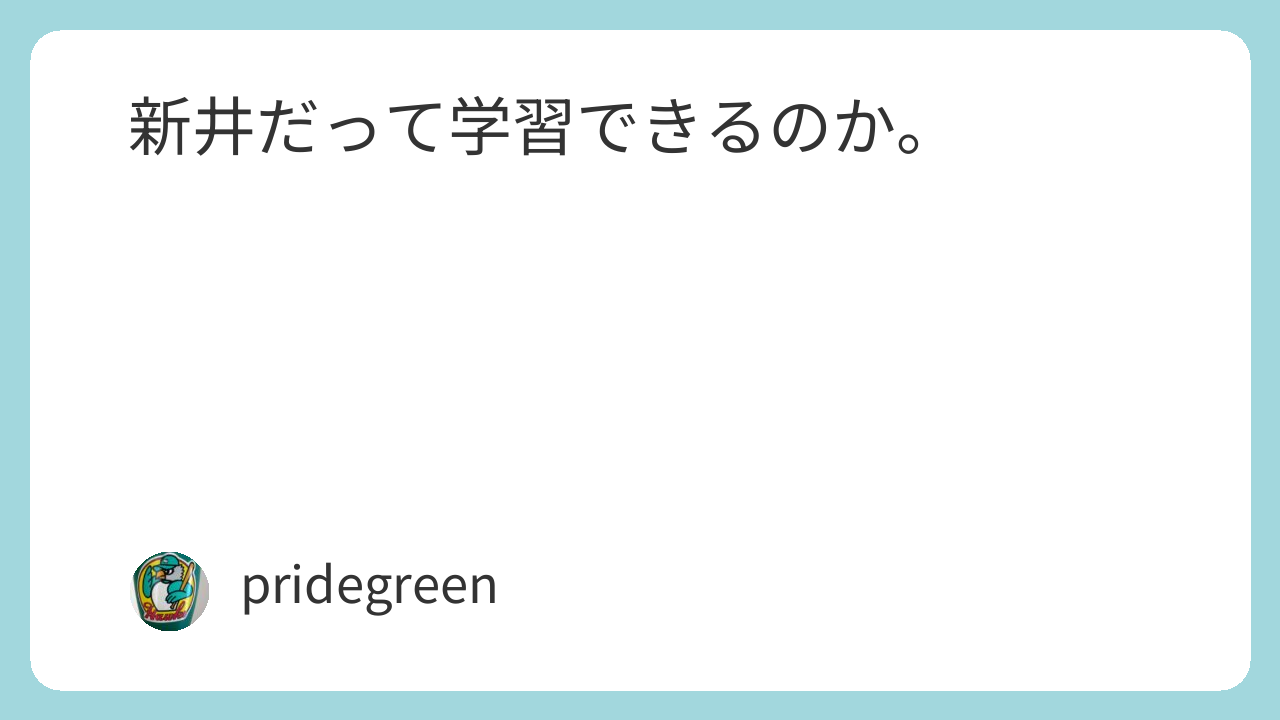
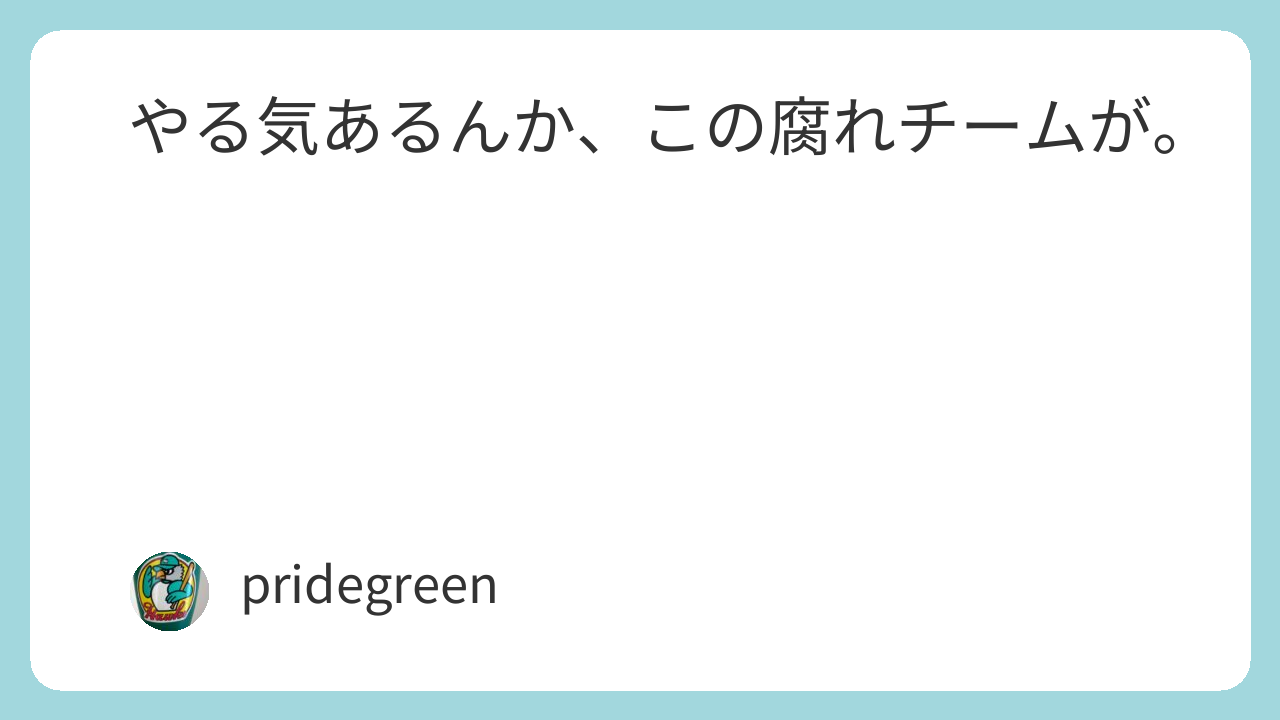
コメント
なぜ、高速球がうちにくいか、半速球が打ちやすいか、物理的に説明すると(苦手な方はスルーで)。
1. 反応時間の限界
• 投球速度 v、投手から打者までの距離 d(約18.44 m)とすると、ボール到達時間
t = frac{d}{v}
例:150 km/h(= 41.67 m/s)の速球の場合
t = frac{18.44}{41.67} approx 0.442 text{秒}
一方、120 km/h(= 33.33 m/s)なら
t = frac{18.44}{33.33} approx 0.553 text{秒}
言うまでもなく、約0.1秒の差が打者の判断・スイング準備に大きな影響を与える。
人間の視覚反応時間は約0.2〜0.3秒。つまり、判断・スイング準備・実行までの猶予が極めて短い。
2. 運動量の増加と衝突制御の難しさ
• 運動量 p = mv(質量 m、速度 v)
• 同じ質量でも、高速球は運動量が大きく、バットとの衝突時に反発力や方向制御が難しくなる。
• 芯を外すと、打球のエネルギーが逃げてしまう。
3. 相対速度とタイミングの精度
• バット速度 v_b、ボール速度 v_p の相対速度が大きいほど、衝突時間が短くなり、打球角度の制御が難しくなる。
• わずかなタイミングのズレが、ファウルや空振りにつながる。
4. 衝突の物理:反発係数とエネルギー伝達
• バットとボールの衝突は、反発係数 e を用いて表される
v_{text{after}} = e(v_b – v_p)
• 高速球では、衝突時のエネルギーが大きいため、芯を外すと打球速度が極端に落ちる。
5. 動体視力と視覚処理の限界
• ボールの回転(スピン)や変化を視認するには、網膜上に十分な時間と解像度が必要。
• 高速球では、ボールが視野を通過する時間が短く、回転数や軌道の認識が困難。
補足:人間の限界
• 人間の視覚反応時間は約0.2秒。
• 150 km/hの球では、ボールが到達するまで約0.44秒しかないため、視認 → 判断 → スイングの一連の動作が極めて困難。
こうして見ると、高速球が打ちにくいのは、単に「速いから」ではなく、物理的な制約と人間の限界が複雑に絡み合っているのだ。
じゃー、高速球が来れば諦めるのか?いやいや、高速球は諦め半速球しか打てんのなら、プロちゃうやん。
高速球を打つ対策と訓練法はある。
1.早めの始動とトップの形成
•投球モーションに入った瞬間に始動し、トップの形を早めに作る。
•トップが遅れると、スイングの準備が間に合わず、手打ちになりやすい。
•下半身を使ったスイングを可能にするためにも、始動のタイミング調整は最重要。
2.動体視力の強化
•ボールの軌道・回転を視認する力を鍛える。トレーニング例は。
•パンチングボールや卓球で目の追従力を鍛える
•雨天時や室内でもできる視覚トレーニングを継続的に実施
3.狙い球の絞り込み
•すべての球種に対応しようとせず、ストレートに狙いを絞る。
•バッターボックスの後方に立つことで、ボールを見る時間を稼ぐ(約10球分の距離差)。
•変化球との見極めも容易になり、スイング準備の猶予が増える。
4.すり足・ノーステップ打法の導入
•足を上げるフォームはタイミングがズレやすいため、すり足やノーステップ打法で目線の安定と始動の柔軟性を確保。
•地面との接地時間が長くなることで、スイングの安定性が向上。
5.実戦的な球速慣れトレーニング
•バッティングマシンで球速を上げて打ち込み。
•マシンがない場合は、近距離から投球して球速感覚を再現。
「慣れ」が最大の武器。普段から150km/h超の球速に触れておくことで、試合での違和感を減らす。
2024秋季キャンプで1000スイングのロングティーとティー打撃???バッカじゃないのー。
死に球打って手のマメを潰す等、身体を痛めつけるくらいなら、家で寝ているほうが余程いい。
セリーグには6球団しかない。それなのに24年間も優勝がなかった。(3連覇後も、今年まで?7年間優勝無し)
NPBは12球団しかない。それなのに今年まで?41年間!も日本一無し。
カープ球団が、日本一になろう・優勝しようと思ってないのは明らか。
テメエが操ってるくせに、監督や選手のせいにさせてほおかむりするマツダハジメ。
生きてるうちに、カープの日本一見られるかな~(涙)