昨日の話の延長戦である。昨日戴いたコメントにインスパイアを受けてひとつ仮説を立ててみた。あくまで仮説であるので、正しいという自信はない。というより、正着手があるかどうかすら分からない道を歩んでいるようなものだ。まあ、雑談の延長ということでお読みいただければ幸いである。まあいつものことだが。
昨日、M-1グランプリのチャンピオンの漫才にクスリとも笑えなかったという話を書いた。別に今回の漫才がどうだというわけではなく、最近のお笑いさんはみんなそうだ。笑いたくても笑えないのである。なんでこんなの売れてるの?という感じしかしないのである。その理由を自分なりに考えてみたが、どうも腑に落ちる結論が得られない。しかし、ある仮説を立てた。
結局のところ、芸人さんがどうこうというより、我々の笑いのレベルが下がってるのではないか。芸人さんも、いや芸能人全般そうなのだろうが、我々の映し鏡になっているところがあるのではないか。
私は兵庫県赤穂市という一応大阪キー局のテレビが映るところで育ったから、笑いと言えば上方のそれである。今でこそ上方落語に傾倒しつつあるが、もともとは漫才で、あるいは吉本新喜劇が紡ぐ笑いで育ってきた。それはみんなそうだ。笑いは常に生活のベースにあった。まして大阪のど真ん中ではもっとそうだろう。よくみんながボケとツッコミを弁えているといわれるが、確かにそうかもしれない。
なので、芸人さんの面白くない笑いには厳しいのである。舞台の漫才とかで面白くなくて笑ってくれないのはいい方である。故喜味こいし師匠の思い出語りによると、戦前の舞台では下手な漫才にはヤジどころの騒ぎではなかったそうである。まあそれはさておくとしても、金払ってるんやからうちらよりおもろいもん見せてえなあというところなのだろう。
私は漫才と言っても、もちろんエンタツアチャコ先生の芸など見てようわけもないが、残されている音声を聞くに、座付き作者だった秋田實翁と目指した「無邪気な笑い」がその鍵にある気がするのである。言い換えるならば、誰でも理屈抜きで笑える笑いがベースにあると言って良いのではないか。ただし、それに至るまでの「万歳」が聞くに堪えない下ネタのオンパレードだったからということはおさえておかねばなるまいが。それを変えたのが砂川捨丸先生である。
話を戻すと、今の漫才さんやお笑いさんにはその点が欠けているといわざるを得ない。要するに、楽屋ネタの延長なのだ。本来舞台でかけるようなネタでもなくそもそも見せられるほど面白くないようなのが堂々と出てくるのである。もはやしゃべくり漫才といううものが姿を消して久しく、ほとんどが劣化版シットコムだ。中川家やますだおかだまでかな。漫才と言えるのは。彼らもヴェテランの域に入ったし、その上の世代であるやすよともこなんてもはや大御所である。
それを許しているのも、結局我々の笑いのレベルが下がったからかもしれない。ニワトリが先か卵が先かの議論かもしれないが、芸人さんのレベルが下がったからなのか、笑いへの感度が下がったからなのか。多分その両方だろう。きっとその相乗効果が現れているに違いない。
東京の笑いに関しては置くとして、上方の笑いをおかしくした元凶はダウンタウンだと思う。念のために言うが、彼らの漫才はめちゃくちゃ面白かった。松本人志の予測不能なボケとそれに半ば暴力的なツッコミを入れる浜田雅功という構図が完成していたし、その完成度も高かった。しかし、彼らは漫才を放棄し、二流芸人を侍らせて疑似ファミリーを作り始めた。それからの劣化ぶりは、見るに堪えない。そのファミリーから脱却し、修行の上ひとつの芸を完成させた山崎邦正こと月亭方正がひとつの証左かもしれない。
もうひとつ致命的なのは、彼らが、いや吉本興業が為政者に阿ったことである。権力にすり寄った笑いはいかに劣化するかということの例には事欠かない。何も反権力でさえあればいいとは言わないが、強い者に対する風刺の精神なくして何が笑いかと言いたくもなる。例えばアホ役やボケ役なんて、アホな権力者が威張りだしたら真っ先に粛正されるのである。
まあ長くなったのでこのくらいにしておこう。要するに、我々の日常にもユーモアがもっとあって良いのだろう。座談でいかに笑わせられるかというのもひとつの能力であり、それを評価できない組織は腐っているのだ。逆に言えば、いかに今の我々の日常はギスギスしてくそ真面目であることだけ求められているかということだろう。それに一矢報いたくて、私は時に弊ブログに小ネタを挟むのである(結局言いたいのはそれかい)。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング
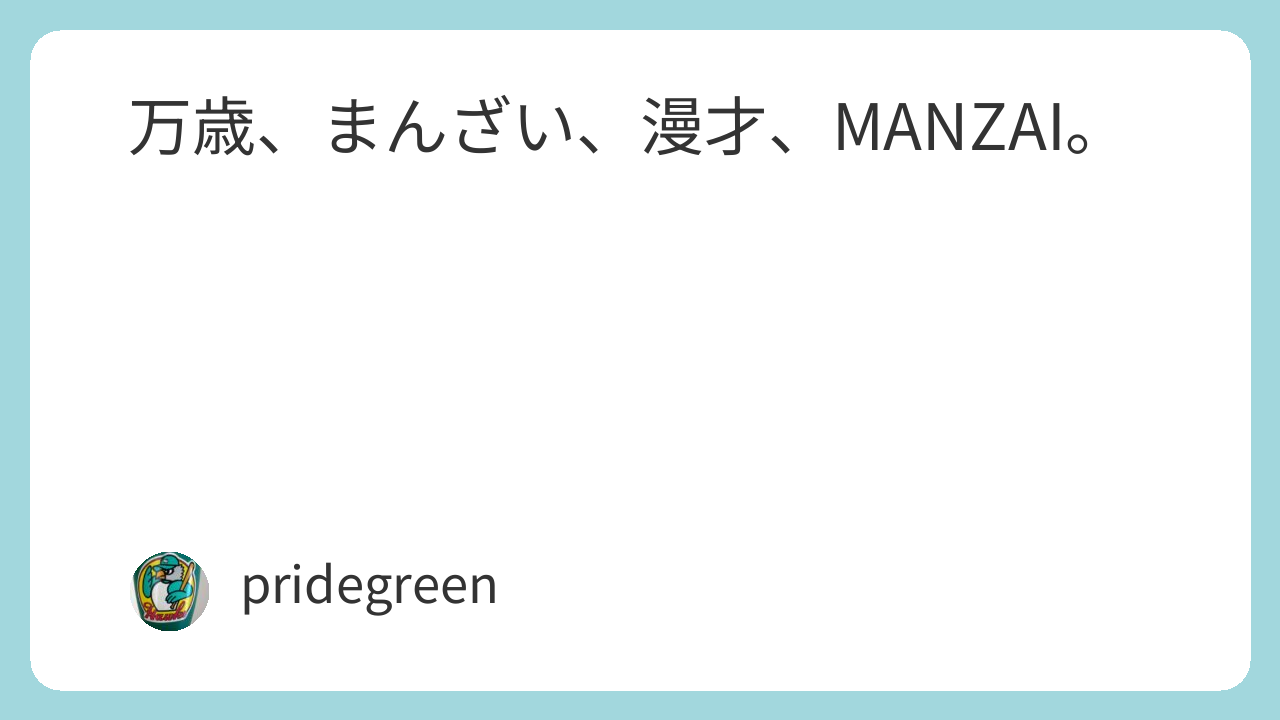
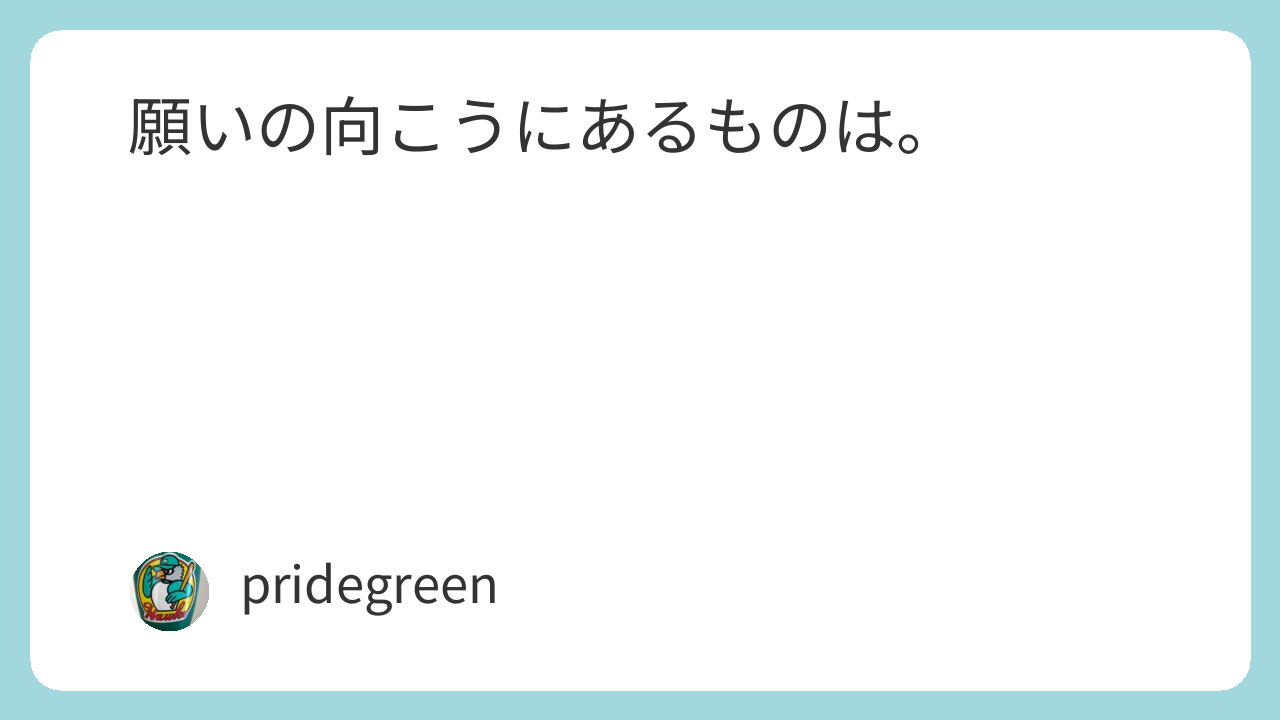
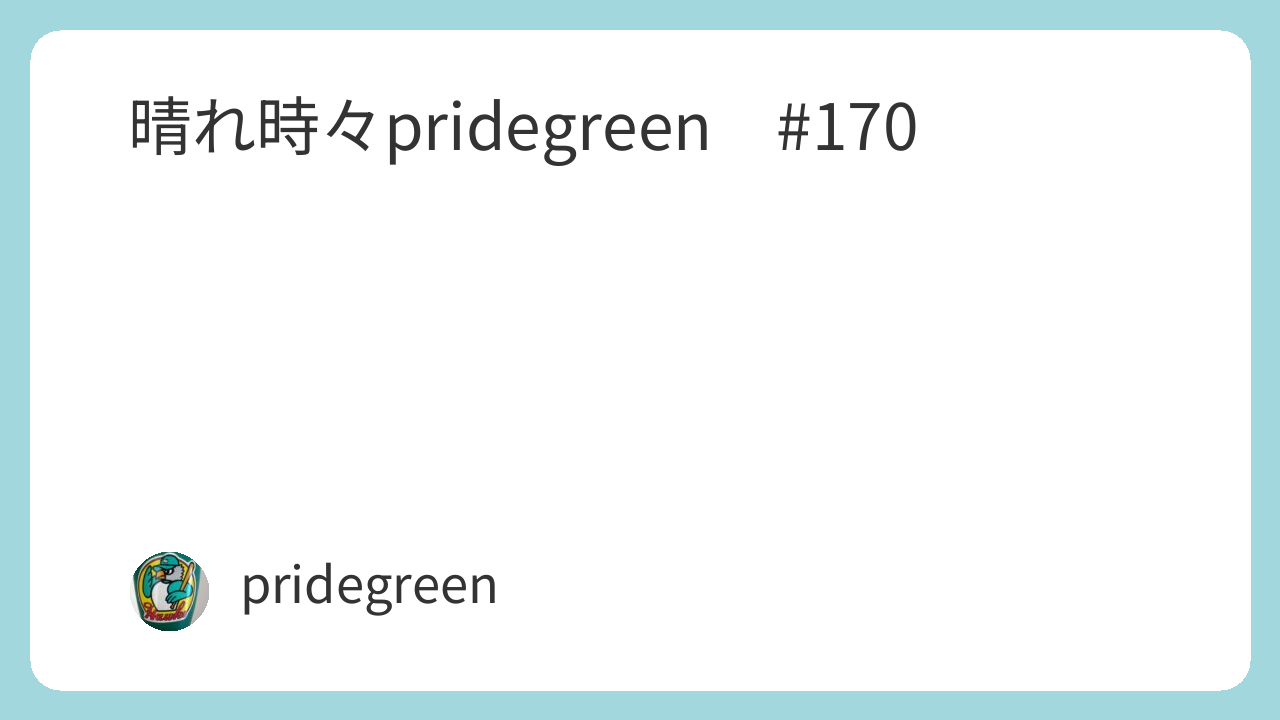
コメント
「座談でいかに笑わせられるかというのもひとつの能力」は仰る通り。
両人は本気でいがみ合う関係なんだけど、周りの者が見ていてオモロイ一般人対決は、婉曲・刺し言葉の京都人女性vs直球・毒舌の大阪人女性。
パート勤務で職場に来ている2人だけど、何かにつけやり合う会話がオモロイ。
[仕事の進め方で衝突]
「大阪はん、昨日の資料ずいぶん賑やかに作ってはりますのねぇ」(内心:ごちゃごちゃして見にくいわ)。
「京都さん、賑やかて何やねん。はっきり“見にくい”って言い!そしたら直すから!」(内心:遠回しすぎて意味わからん)
「いえいえ、うちらにはちょっと刺激が強いだけどす」(内心:派手で下品やわ)
「刺激て!アンタの資料、白黒で眠なるねん!ちょっとは色使いぃや!」(内心:地味すぎるねん)
[昼休みの雑談で温度差が爆発]ちなみにパートは社食利用不可
「大阪はん、お昼、コンビニのお弁当どすか?お忙しいんやろなぁと思いまして」(内心:料理できへんの?)
「京都さん、忙しいに決まってるやん!あんたみたいに優雅に弁当作る暇ないねん!」(内心:嫌味か?)
「まあ……よう働かはりますなぁ」(内心:ガサツやなぁ)
「働かな金入らんやろ!アンタは働かんでも生きていけそうやけどな!」(内心:なんかムカつく)
京都は“温かいふりをした冷たさ”、大阪は“無作法なふりをした温かさ”というOSの違いが職場では最悪の形で衝突する。これが、オモロイ。
他では、皮肉・婉曲・階級的距離感のある英国王公文化のユーモアと、雅を装った“刺し言葉”で婉曲話法の京都公家文化のユーモアの類似性もオモロイ。
英国の上層文化には、次のような特徴がよく指摘される。
• 直接的に言わないことで相手をコントロールする
• 褒め言葉を“逆方向”に使う
• 相手をやや突き放した距離感を保つ
• ブラックユーモアやアイロニーを日常的に使う
英国の貴族文化では、露骨な攻撃は下品とされるため、「相手を褒めることで相手を下げる」
という高度な婉曲攻撃がよく使われる。
例:“Interesting.”(=つまらない)
“You’re very brave.”(=無謀だね)
“That’s ambitious.”(=無理だろう)
つまり、言葉の表面と意味が逆転する文化。
京都の公家文化にも、似た構造がある。
• 直接言わない
• 表面は柔らかく、内側は鋭い
• 相手の自尊心を揺らす“雅な嫌味”
• 特に女性の会話に高度な婉曲性がある
例:「まあ、お元気そうどすなあ」(=最近太った?)
「よう勉強してはりますなあ」(=知識をひけらかしてるね)
京都の“刺し言葉”は、「表面の優雅さ」と「内側の冷たさ」の二重構造が特徴。
二つの文化は“冷めたユーモアの構造”でつながる。英国王公文化・京都公家文化、この二つは「直接言わずに褒め言葉で刺す」という高度なコミュニケーション技法を共有している。
事例:相手の知識が浅いとき
🇬🇧 英国版
A:I read one article, so I know all about it now.
B:Oh, you’re very well informed.
構造
•表面:よく知っている
•内側:浅い知識で語るな
•技法:Irony(逆意味の褒め言葉)
•温度:皮肉が前面に出る
京都版
A:ちょっと本読んだだけなんですけどね。
B:まあ、ようご存じで。
構造
•表面:よくご存じですね
•内側:その程度で語るのね
•技法:“よう〜”は京都では刺し言葉
•温度:柔らかいが鋭い
こうしてみていくと、王公文化と公家文化といった特殊な環境下ではあるけれど、日常的にオモロイねたは転がっている。
いやあ、非常にいい文章ですね。
「いい文章と言われると照れますね。次はもっと長くします」