むかし、「題名のない音楽会」を黛敏郎が司会をしてた時代に、よく指揮者の岩城宏之が出演していた。ある時に岩城宏之翁曰く、ある日試しにベルリン・フィル(だったと思う。間違っていれば失礼)の楽団員に次々と日本の歌謡曲のレコードを聴かせたという。そこはなんと言っても当代一流の音楽家揃い、ほとんどの曲は鼻でせせら笑っていたらしいが、ある曲がかかった途端に全員が目を見開いて聴き入ったという。そして口を揃えて言った。「この曲には力がある」、と。
その曲こそ、美空ひばりの「柔」だった。確かにあの極はお嬢のナンバーの中でも圧倒的な存在感を誇る曲だといっていいと思うが、天下のベルリン・フィルの楽団員をも、その声だけで圧倒したというのはやはりただ者ではない。当たり前だが彼らは美空ひばりがどうたらという先入観が全くないのである。まあ、私より二回りくらい上の世代の人だったら何を当たり前のことをと思われるだろうが。
最近、なんかことあるごとに「歌の力」なる言葉が安売りされているような気がする。確かに紀貫之は「あめつちをもうごかし、めにみえぬおにがみをもあはれとおもはせ」などと言ったが(ただし彼の言う歌とはやまとうた、すなわち和歌だが)、どんな歌でもいいと考えていたのではあるまい。秀歌と凡歌とは自ずと差があるだろう。それは事実仮名序での辛い歌人評に現れている。
ましてや、今の「歌」、すなわち歌謡曲はそうだろう。人生さんではないが、今の日本の歌の中で、どれだけ「力」があると思える曲があるだろうか。私に言わせれば粗製濫造の極みである。これから年末にかけてまた歌を聴く時期に入るが、常々思うのは、その歌は誰に対して歌ってますかということだ。
はっきり言う。最近の歌は、すべからく「一部ウケ」だ。もっと悪く言えば「自己満足」、さらに悪く言えばMasturbationである。もちろん自分で納得できないような曲を人前にかけることなど出来ないだろうが、ものすごく低いレベルで納得してこれすごいだろうと見せつけている趣なのだ。控えめに言って、聴くに堪えないというところだろうか。
今となってはタレント扱いだが、やしきたかじんというのは非常に得がたい歌手だった。全盛期の彼の歌は、本当に人を引きつけるものがあった。引きつけられた中の1人が言うまでもなく私だ。彼はレコーディングのとき3回までしか歌い直しをしなかったという。もちろんそれだけ完璧に仕上げてくると言うことである。ただ、全盛期は短かった。1985年から1994年までの10年間が一番艶があったが、やがて声が衰え、そのうち歌に興味を示さなくなってしまった。
今や歌というのは、キャッチーなフレーズをSNSでバズらせるためだけの物になってしまった。いや、そういう曲の作り方が悪いわけではない。それを芸術に昇華させたのがキダ・タローという人であるし、つんく♂なんかはキダ・タローの影響を受けているのではないかという気がする。しかし、今聞こえてくる曲はすべからく外形だけ真似た水割りだ。
最近私は、たかじんとももクロ(彼女らは決して歌はうまいとは言えないが、前山田健一の才能が光る)を別としたら、ふるっぱーやきゅーすと、きゃんちゅーをたまに聴いている。理由?正統派アイドルという路線を徹底して売っているのがよい。そこまで突き抜けると歌の巧拙を超える説得力が出てくるのだ。
と、いうわけで、12月31日の紅白である。他に見るものがないからきっと見るだろうが、楽しみはないし、きっと何を聴いても右から左だろう。去年はB’zとTHE ALFEEという飛び道具で面目を保ったが、今年はどうするつもりなのかね。従前はもう12月31日の23時45分にはおなかいっぱいになっていたのだが、今年はどうなるんだろう。水を飲んで腹を膨らませる趣になりそうだ。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング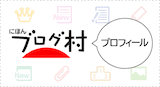
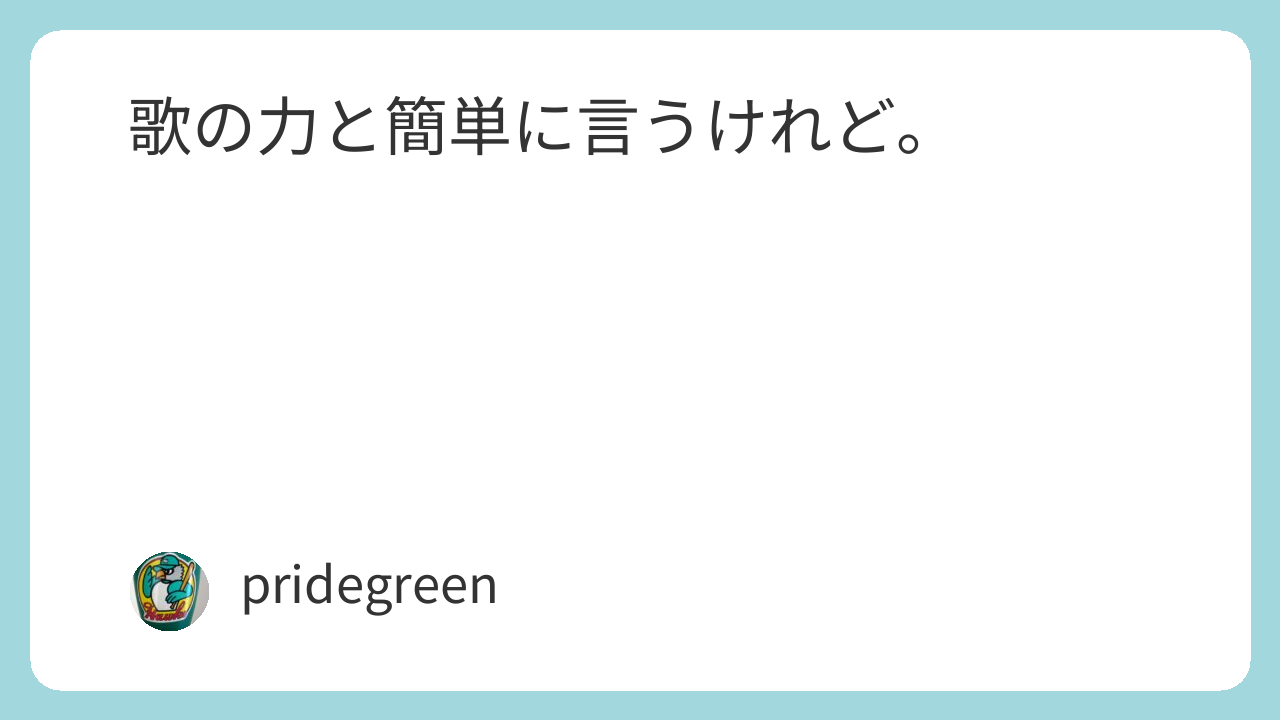
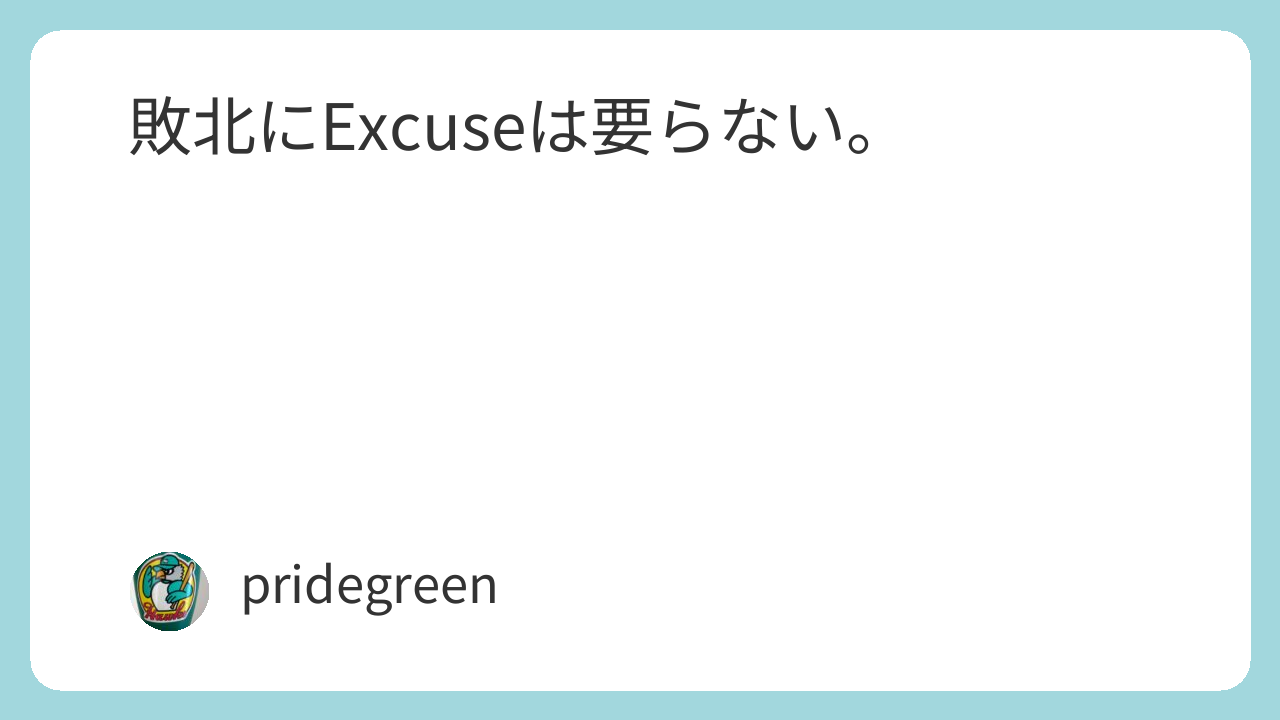
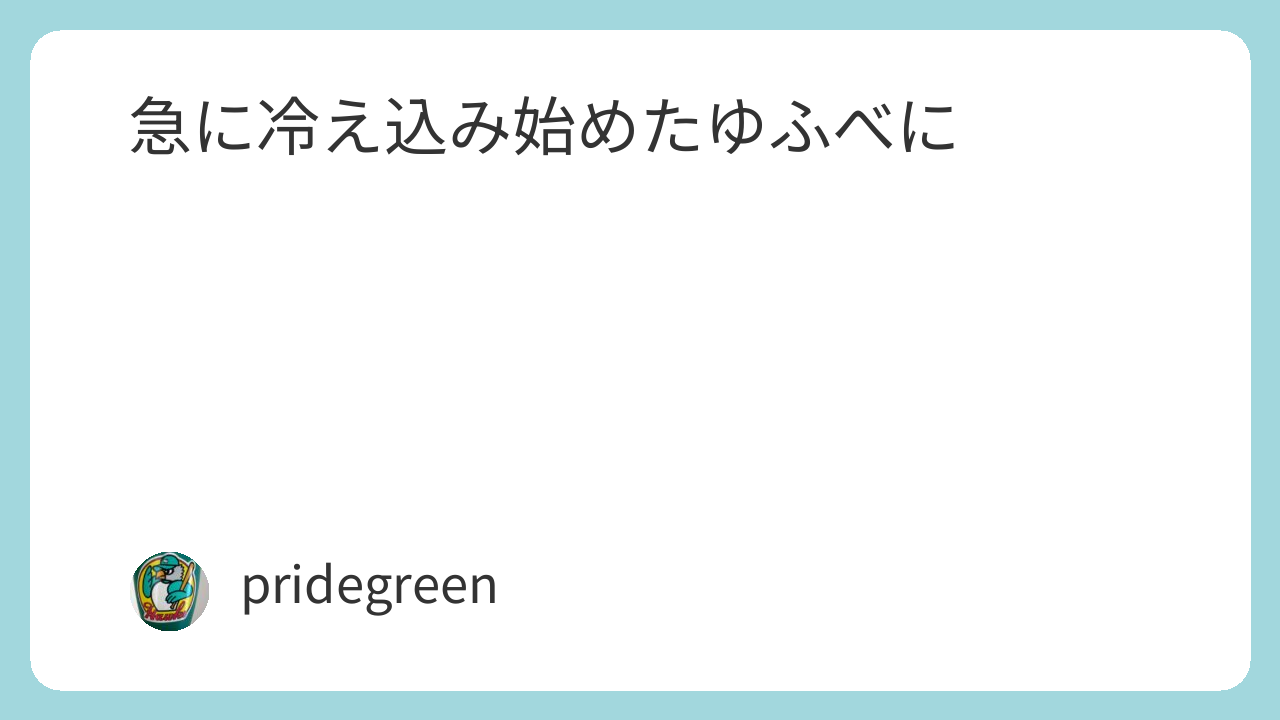
コメント
美空ひばりの発声、取り分け低中音域はチェストボイス(地声)で太く鳴らすので、力強く聞こえたのでしょう。ベルリンフィルが普段共にするのはオペラ歌手で、歌謡曲歌手とは根本的な発声法が異なります。オペラ歌手の発声法はベルカント唱法で、腹式呼吸が基本中の基本。具体的には、横隔膜を使ってお腹から息を吸い込み、声を出すことでより多くの空気を使い、安定した声を出すことが可能になります。もう1点、日本のオーケストラのピッチは442Hzで、ベルリンフィルのピッチはカラヤン時代から446Hzを採用しています。歌手のバックオーケストラのピッチ差が4Hz=約16セント(半音の6分の1強)も違えば、ベルリンフィル団員のような訓練された耳には、異次元の音楽に聞こえるのは当然です。
美空ひばりの中高音発声もチェストボイス(地声)で、地声域以上は綺麗にファルセットへ移行させています。歌謡曲歌手は、地声からファルセットに切り替わった瞬間が完全に分かっちゃいますが、プロのオペラ歌手の発声は、一貫して「ベルカント(美しい歌唱)」の理念に基づき、声区の移行を極力聴き手に悟らせないように設計されています。まあ、どちらのファルセットも「意図的な表現」であり、技術の優劣というよりは美意識の違いとも言えます。
俺自身は、ベルカント唱法を基本に歌っていますが、オペラが最上位だとは思っていません。ライヴ演奏はヘビメタが6割くらいだし、ヒップホップ・ユニット「Creepy Nuts」のコピーもやります。年1で雅楽の舞台にも立ちます。他、ちょっと辛い任務ですが、知り合いのホスピス院長から依頼があれば、推定余命14日以内の方のリクエストに応える形でアカペラ仲間2~3名と「ラストソング」を届けに行くことが年に数回あります。先週11日は、大腸癌末期30代女性からのリクエストで”思いがかさなるその前に”を手向けてきました。
年末の紅白歌合戦といえば、両親が楽しみにしていて、子どもの頃は何となく一緒に観ていたものですが、気づけばもう半世紀もご無沙汰です。
20代半ばから30数年間、年末は物好きなアカペラ仲間が居れば練習場所のカトリック教会でモツレクを歌うか、仲間が居なければ1人で聴きながら年を越す感じですね。
指揮:ミッシェル・コルボ
演奏:ローザンヌ声楽アンサンブル
ソプラノ:エフラート・ベン=ヌム
アルト:エリザベス・グラーフ
テノール:ジェフリー・フランシス
バス:マルコス・フィンク
このモツレク、小編成で「響きの美しさ」では随一の名演&名盤です。録音(1995年)が良く小編成の演奏で透明感があります。おそらくモーツァルト時代の編成にも近いと思います。