今日は選手権の決勝戦があり、沖縄尚学が日大三高に勝って優勝した。それはさておき、夏の選手権が終わると、子どもの頃なら途端に夏休みの終了を告げる寂寞感を感じたし、今でも夏の終わりを告げる区切りのような気がする。以前も書いたが、夏の選手権は晩夏の祭典であり、秋の訪れの前触れとなるところが、選抜と異なる。
高校野球の歌といえば、西浦達雄さんの歌というのが定番だったのだが、これも終了してだいぶん年がたつ。そういえば大定番だった「君よ八月に熱くなれ」ですらめっきり聞かなくなった。そんな中、高岡健二さんが歌った初代「君よ八月に熱くなれ」のB面に「真赤な風」がある。まさに夏の終わりを告げる名曲であって、アベロクさんがよくかけていた記憶がある。実は今日の標題は、この歌のサビから頂戴したところである。
なんでこれを引っ張り出してきたかって?言うまでもない。今シーズンのカープは完全に終わった。まさに自らペナントレースの終わりを告げたのである。まだクライマックスシリーズ圏内だって?寝言は寝てから言おう。今日みたいなクソみたいな試合やって、なにがクライマックスシリーズなものか。鼻で笑われるよ、他球団に。
本来なら逐一駄目さ加減を取り出してやりたいが、今日は腐ったチームの腐った野球なんかほったらかして、最上の仕事と至高の味に舌鼓を打っていたから、その余韻が壊れるようなアホな真似はしたくない。心あるファンならその思いは分かってくれるだろう。なので、書かない。こんな試合をいい試合だと思えるほど、私の感性は腐ってないと信じたい。
ひとことだけいうと、今日はね、ドラゴンズに舐められてたんだよ、最初から。2番樋口、8番加藤。宏斗出したらこんなもんで余裕と言われてるようなもの。にもかかわらず、それにそのとおり嵌ったカープは本当に莫迦だ。
もちろん今日の試合は見ていないし、録画で裏を返そうという気なんてないが、やはり昨日の敗北が与えた影響は大きいのではないか。やっている選手の気力を失わせるには十分だっただろう。私がプレイヤーだったら、指揮官新井なんて信じるに足りないと思ってしまう。
というわけで、今のカープの選手にかける言葉は、まさに標題のとおりに帰する。まあ、来年の3月末にもう一度。いや、戻ってほしくない選手も多数いるんだけどね。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング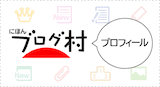
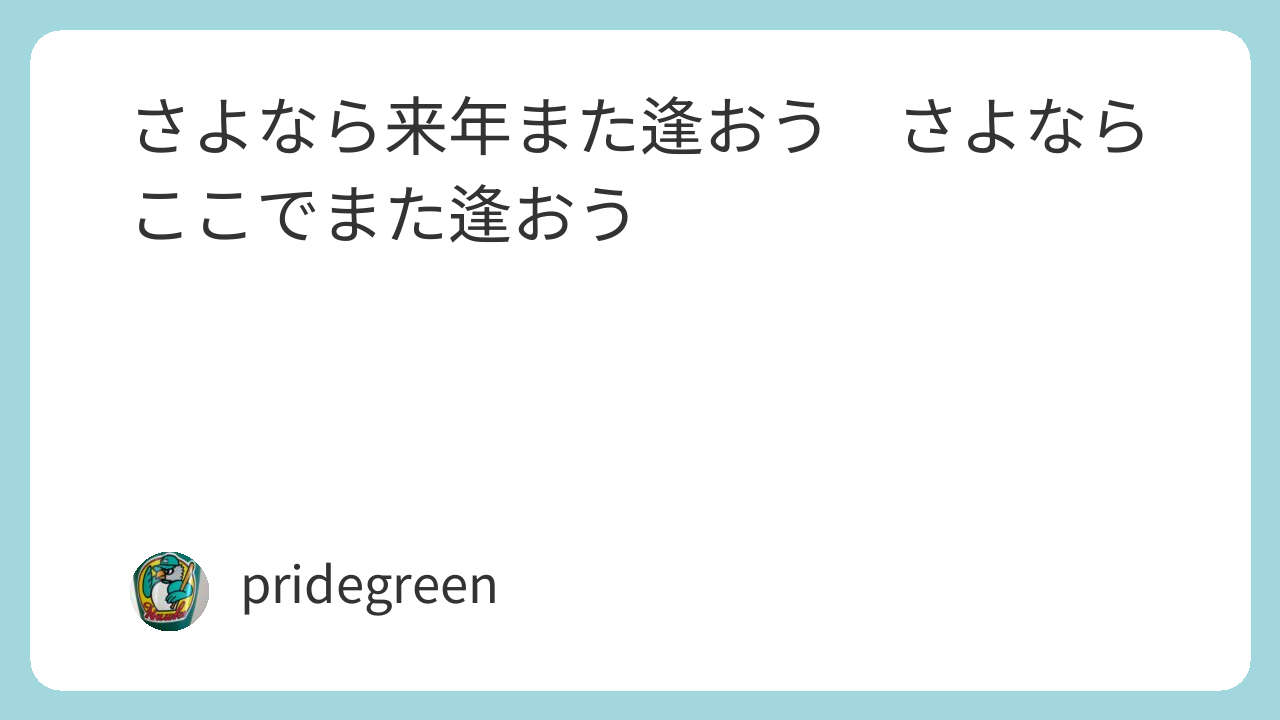
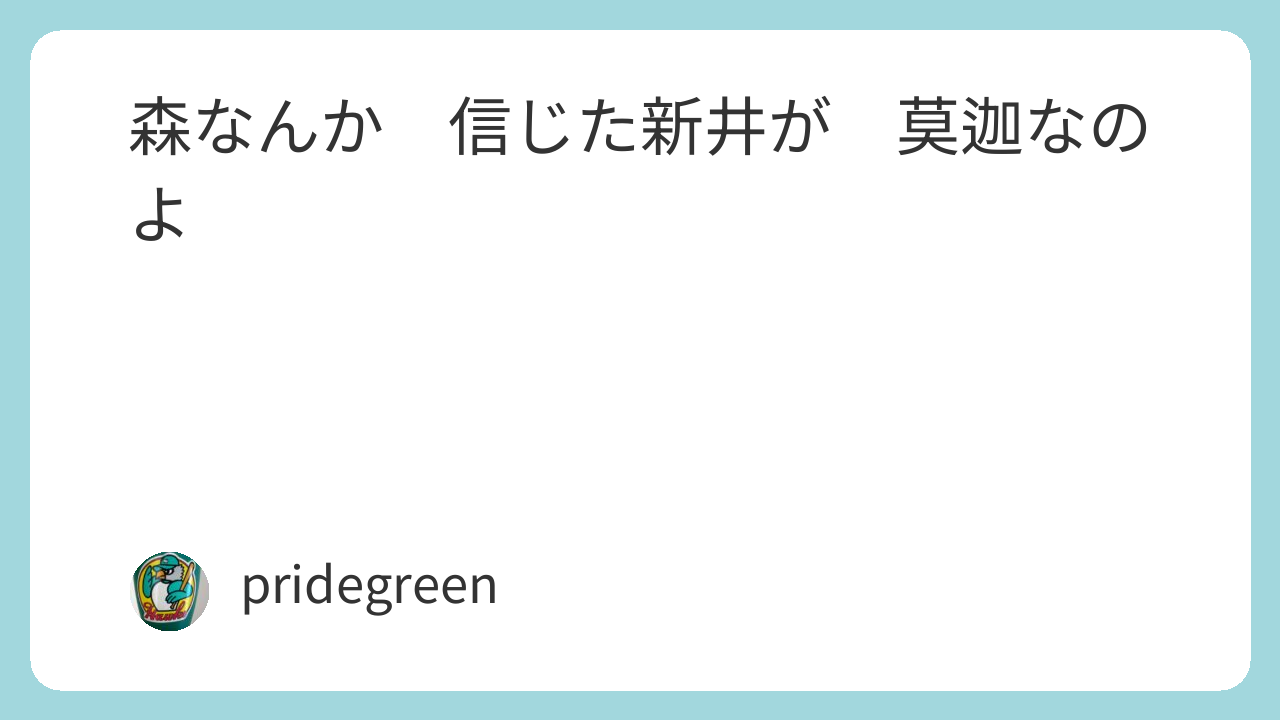
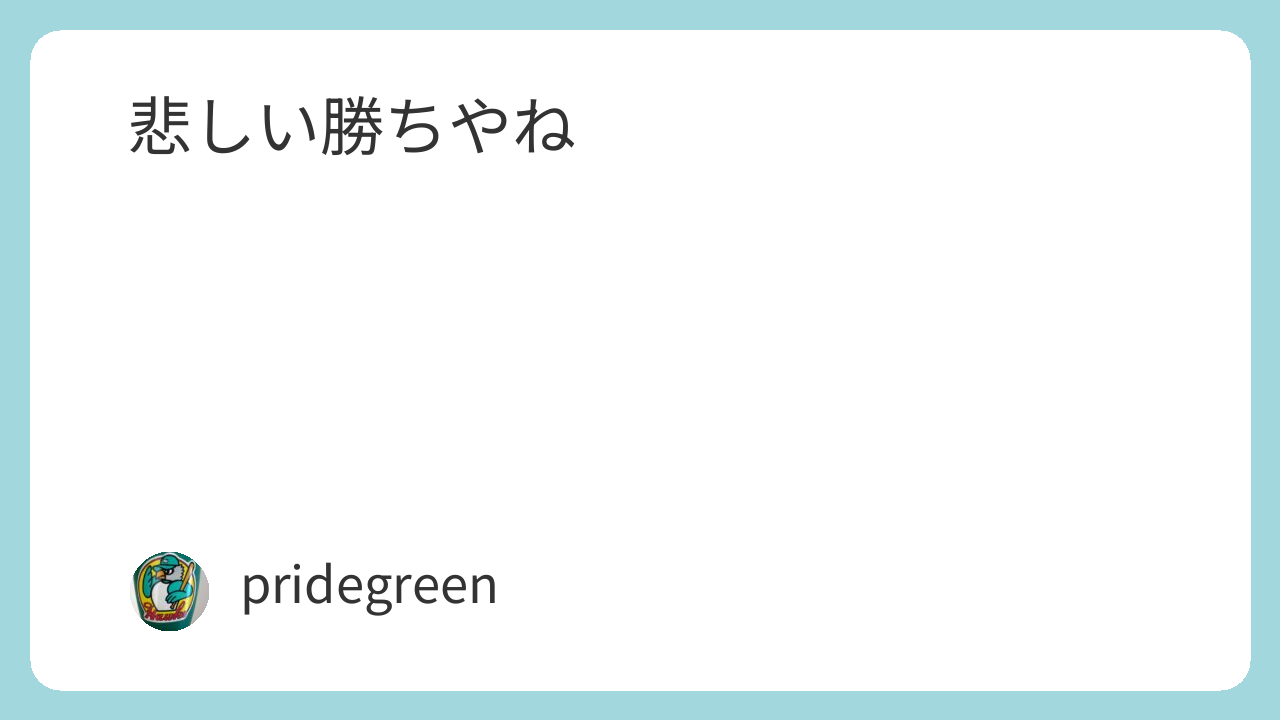
コメント
この時期になると、何となく森山直太朗の「夏の終わり」を聴くことにしているが、23日はボイトレ、チェロ実技、ソルフェージュのレッスンを行ってる藝大声楽科受験予定2名&藝高チェロ専攻受験予定1名が駅前広場でミニライヴを開くという話を聞いていたので手伝うことにした。
音楽系において日本最難関の大学と高校を受験するレベルになると、即興演奏が出来て当たり前なので、聴衆のリクエストにその場で応える形式にチャレンジ。
1曲目が”Creepy Nuts”の「Bling-Bang-Bang-Born」。この曲はオリコン年間ランキング、合算シングル・デジタル・ストリーミングの3部門で1位を獲得・3冠達成した快挙で年代を問わず影響力が大きかった。めっちゃノリがいい曲で、冒頭の楽曲としてはベスト。リクエストされた方はセンスがある。
2曲目が「ハナミズキ」。季節が違うんだけど、ま、いいかぁ、と。一青窈がこの詩を作ったきっかけは、2001年のアメリカ同時多発テロ事件。「君と好きな人が百年続きますように」というフレーズは、命の尊さと平穏な日常への願いを象徴している。ハナミズキの花言葉には「永続する愛」「返礼」などがあり、失われた命への鎮魂と希望の再生を重ねたか?(率直なところ俺、反戦歌は苦手だが、花としてハナミズキは好きだから、ぎりぎりセーフ?)
3曲目が「秋桜」。9月に結婚予定の女性が母に贈る歌としてリクエストされた。この歌は、単なる母娘の別れではなく、「女性としてのアイデンティティの継承」や「家族という制度の中での個の揺らぎ」をも描いているとも言える。娘が母のレールに乗ることへの葛藤、そしてそれを受け入れる瞬間の静かな決意。まさに、「制度と個の交差点」が凝縮された作品。聴衆の一部からすすり泣きが響いていた。
ラストが「夏の終わり」。まるで聴衆の中にサクラが居たようなリクエストだが、偶然と言うしかない。
一聴すると恋愛や季節の移ろいを描いた叙情的な曲なんだけど、実は俺の苦手な反戦歌なんだよねえ。8月15日と重なる「夏の終わり」という時期設定が、戦争の記憶とリンクしている。歌詞の中にある「焼け落ちた夏の恋唄」「忘れじの人は泡沫」などの表現が、戦争によって失われた命や愛を象徴している。松尾芭蕉の句「夏草や兵どもが夢の跡」を連想させたかったのか?戦争によって消えた繁栄や命への哀悼が込められている。ような気がする。
まあ、俺の中で「反戦歌を披露するなら戦争当事国(例えばクレムリンと赤の広場)に行って命懸けで歌え」という主義なんで、安全地帯から綺麗事を並べて自己満している人々には虫唾が走る。
それでも森山直太朗の「夏の終わり」は、学童期に過ごした田舎(香川)の、水芭蕉が揺れる畦道、笹舟、夕暮れ、風鈴、蛍火など、日本の里山や田園風景を思わせる言葉がちりばめられ、日本の原風景と記憶の層が織り込まれた詩は美しい。