昔マリーンズの応援曲は、有名曲の引用が非常に多かったのだが、1995年から今の「マリサポ」スタイルに変わった。今のマリーンズの応援曲の中で最も響くのはネフタリ・ソトのそれだろう。元歌のそれと相まった宗教的な響きすら感じる。その元歌はJagwar Twinの”Happy Face”らしい。
ところが、このサビのメロディはuniqueなものではない。実は妻が車で聴いていたCDの中にINNAの”Cola Song”という歌があり、そのサビ部分がこれとそっくりなのだ。もちろんアレンジとか曲の世界観は水と油ほど違うが。ちなみに、できたのはこちらが先だ。これを聴いて、私は納得した。
今は保守派文化人だったくらいにしか思われていないが、黛敏郎(日本テレビスポーツテーマの作曲者でもある)がかつて「題名のない音楽会」で、こういう似たもの音楽ができる理由を話していたからだ。すなわち、①他人の空似②意図を持った引用③何かのはずみ頭に残っていたメロディが無意識に出てしまう④悪意を持ったパクリ、である。たぶんこれは①か③のどれかなんだろう。そして、洋楽の間でも起こりうることであると。
中には頭が悪いのがいて、日本の歌はすべて洋楽のパクリだと言って憚らないのがいるが、ちゃんちゃらおかしい。そもそも基本の音は12個しかなく、それを耳に心地よくするためには単なる順列組み合わせではすまない、必然的に似たようなメロディが残るということに知恵が回らない向きは、心底軽蔑する、というか哀れだと思う。
そんな向きに聞かせたいのが、金沢明子が歌った「イエローサブマリン音頭」である。大瀧詠一プロデュース、訳詞松本隆、編曲萩原哲晶で作られたのだが、なんと言っても萩原哲晶翁の編曲が秀逸だ。イントロからして抱きしめたい(ビートルズ)→錨を上げて→軍艦マーチ→スーダラ節→おこさ節の5連発である。そしてオリジナルを尊重したうえでちゃんと音頭になっている。これをパクリと言って否定するのはおかしかろう。
それでもおかしいという向きには、ペンデレツキの「トレノス」を聴かせたい。これを聴いて顔をしかめるのなら、二度と人の音楽に対してパクリなどと言ってはならない。まさに唯一無二の世界なんだから。本来なら、ヘルベルト・ケーゲル指揮のものが一番良いのだが。
免疫のない人が聞くと夜トイレに行けなくなっちゃいけないので、本日はお日柄もよろしいので「イエローサブマリン音頭」も貼っておく。
要するに、仮にある曲のメロディに影響を受けて似たようなメロディができたとしても、オリジナルに敬意を持ち、空を自分の曲に染めることに何の引け目を持たねばならないのかと思うし、それを咎める向きは酢豆腐的半可通と言うべきだ。要するに、有害なのだ。
なんとなく似てますな、カープファン界隈に。チームが強くなることを否定して弱いチームを応援することに理論武装して恍惚としている向きが。いけない、今日はこういうことは書かないつもりだったんだ。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング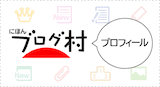
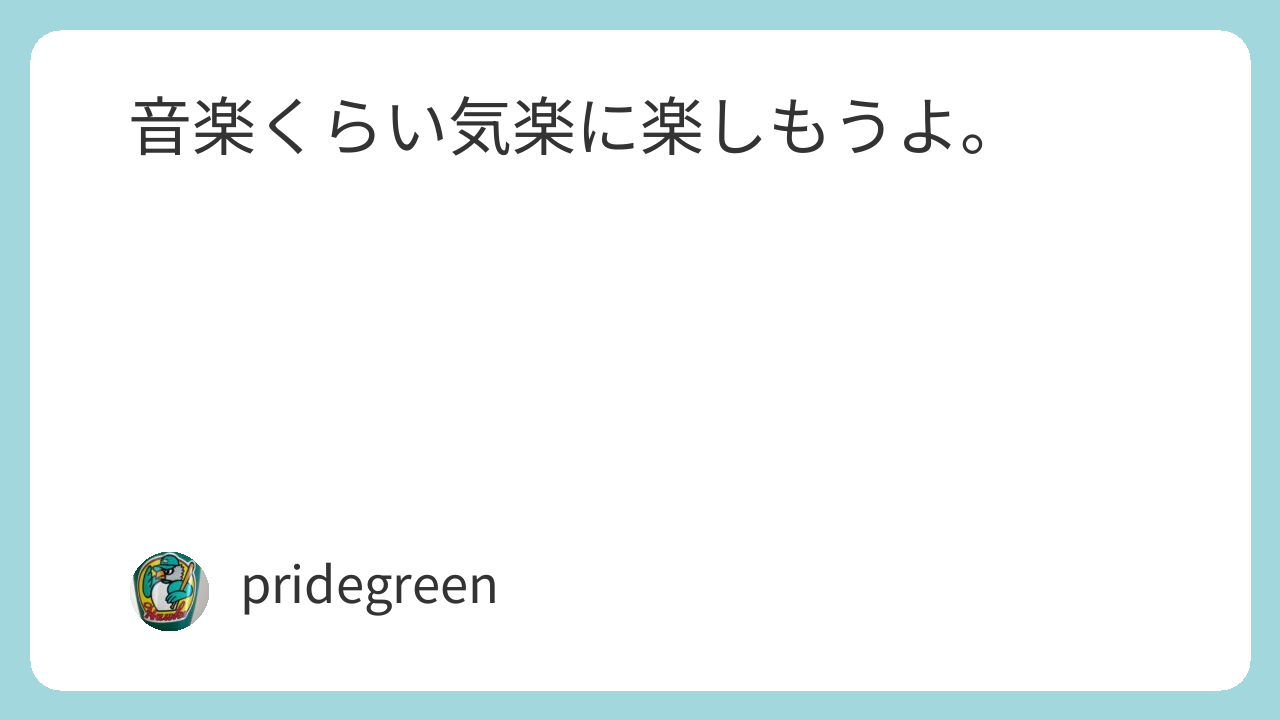
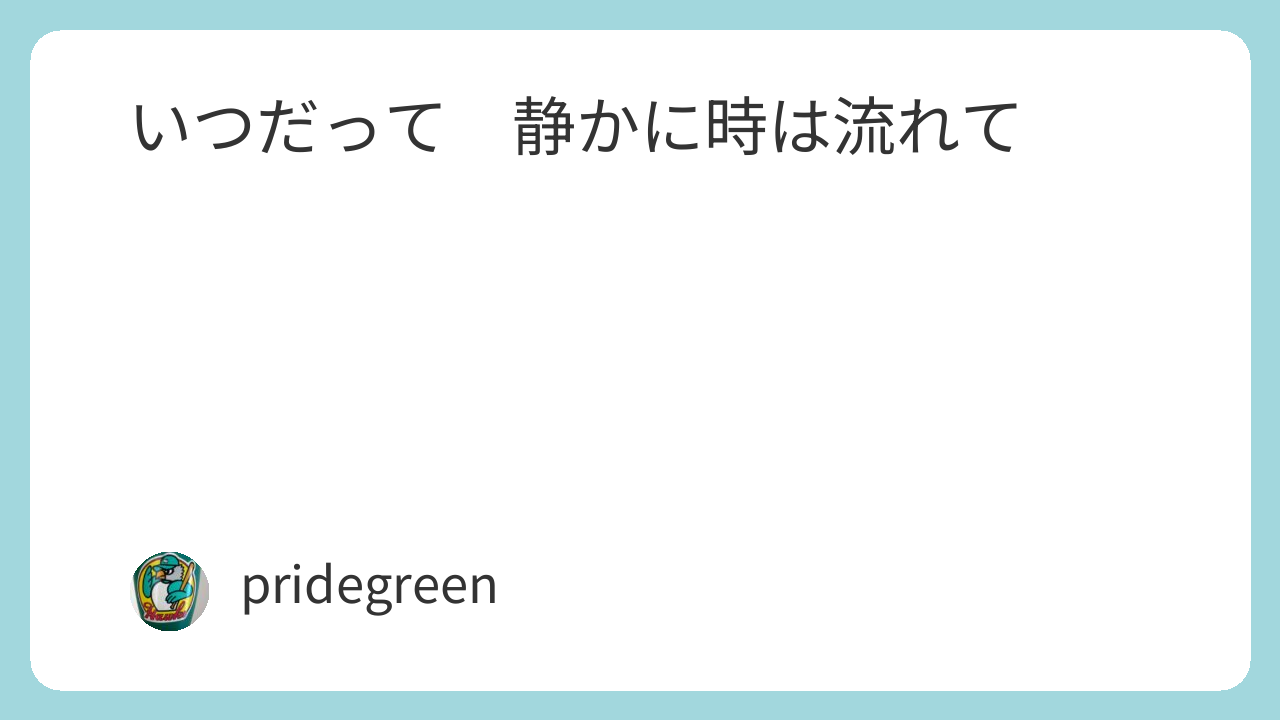
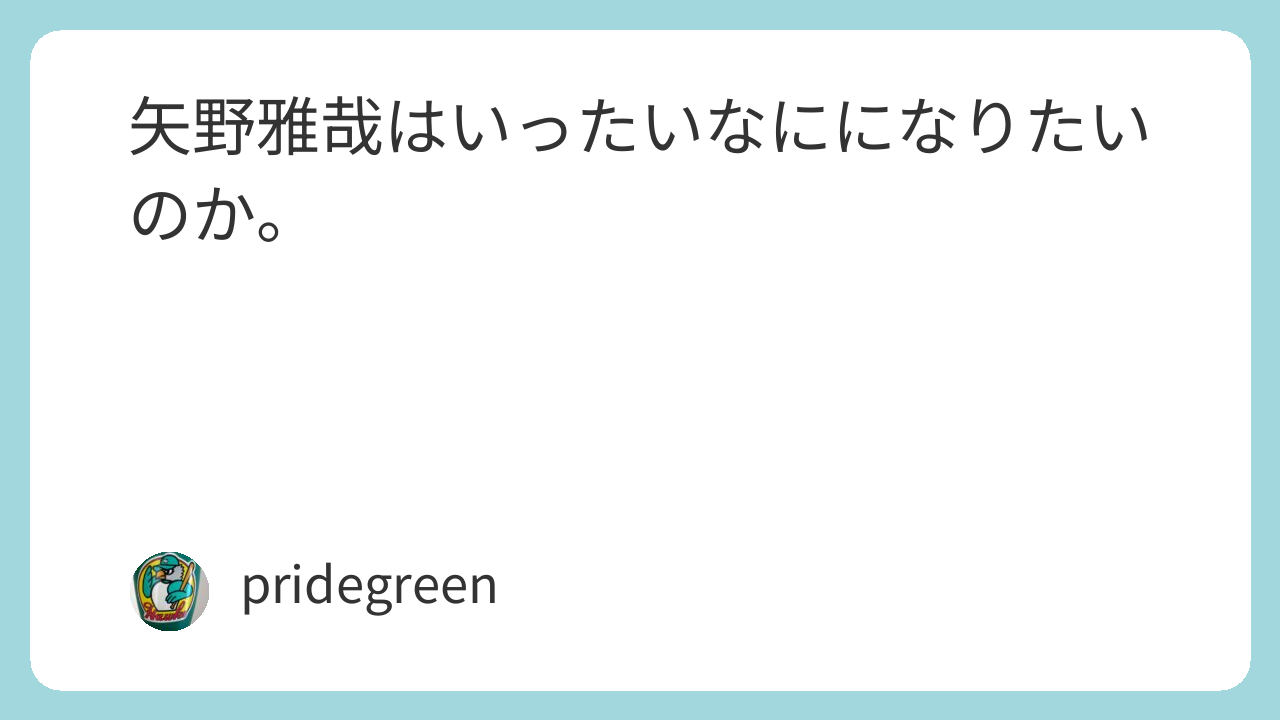
コメント
音楽のパクリは、そんなに珍しいものではなく、クラシック、ロック、ポップス等々あらゆるジャンルで「パクリ疑惑」が浮上している。
【世界のロック】盗作裁判20選 Part1【有罪?無罪?】 YouTube
【世界のロック】盗作裁判20選 Part2【流石にこれは、、】YouTube
音楽史はパクリの歴史?バッハから学ぶオープンソースマインド Webサイト「聖ブレンダンの航海」
B’zの盗作(パクリ)の裁判 no⁺e
ビートルズのようなレジェンドでも、楽曲の盗作・パクリ疑惑が浮上したことがある。
・ビートルズ(ジョン・レノン作)の代表的な疑惑として”Come Together”が、チャック・ベリーの”You Can’t Catch Me”に似ていると指摘され、”Here come old flat top”という歌詞が、チャック・ベリーの歌詞と酷似していたため、訴訟に発展。結果的にレノン側は和解し、チャック・ベリーの楽曲をカバーすることで解決している。
・ジョージ・ハリソンの”My Sweet Lord”は、盗作だとして訴えられた。シフォンズという女性グループが歌って全米で1位になった”He’s So Fine”だ。作曲家ロナルド・マックが書き、音楽出版社ブライト・チューンズが保有していた。ブライト・チューンズはジョージ・ハリソンを著作権侵害で訴えた。裁判は10年間にもおよび、ジョージ・ハリソンが敗訴。約60万ドルもの賠償金を払う事になった。
まあ、裁判に発展するケースも多々あり、何とも言えないが、感想はひと言「ふーん」
音楽で俺が最も影響を受けたのは、ピアニストの祖父・声楽科の祖母ではなく、楽器も歌も全くやらない小中時代の同級生。彼は、あらゆるジャンルの音楽に精通しており、こんなのがアルよ、と薦められるまま一通り聴くことにしている。
例えば
・音響的なノイズや不協和音を主体。旋律やリズムを排除した「ノイズミュージック」
・機械音・工場音・暴力的なビート。反体制的な美学を表現した「インダストリアル」
・複雑なリズムと変拍子。予測不能な展開をする「マスコア」
他にもまだまだ変態チックな(笑)ジャンルがある。
俺のベースはクラシックだけど、ライヴ演奏では北欧のメタルが6割っていう感じかな。
管理人さんの標題、「音楽くらい気楽に楽しもうよ」は、全く以てその通りだと思う。
現在、野球のほうは、パシフィックのCSとMLBの中継をたまに数分観る程度かな。
CSファーストステージで敗退したバファローズにしても、リリーバーの9割が155~160㎞のスピードボールを放る。山下舜平大は先発でコンスタントに158㎞を放るのだからエグい。ファイターズも同様。短期決戦の勝敗の行方は別として、セントラルとは次元が違う。
さらにMLBをちょい観すると、98マイル(約158㎞)放るPは普通で、100マイル(160㎞)超の球を放るPが、それなりに居るので、スピード感満載でエエなぁ。
ジェイコブ・ミジオロウスキー投手の101.4マイル(約163.1キロ)を捉えた誠也の豪快弾は圧巻。101.4マイル撃ちはPS史上最速タイだとか。
数分とはいえ、こういうハイレベルの野球を観てしまうと、チームが強くなることを否定して弱いチームを応援するカープファンが云々という次元の話は、どうでもいいように思えるくらい虚しい。