連休の間は、いろいろとものを考えるには絶好の機会だ。普段はどうしても一番ものを考えるに都合の良い時間が本業で埋まってしまう。なので、連休最終日の今日、少しだけ書いてみようと思う。普段のネタとは違うので、興味のない方はここで引き返していただいて構わない。なお、大学などで「刑法総論」をかじられた方向けであり、それを前提で書かせていただく。
さて、刑事責任が問われる、すなわち刑法により処罰されるべき行為というのは、構成要件に該当し、違法性があり、かつ有責な行為であるというテーゼは、まあ所与の前提のようなものだ。その中で、違法性、すなわち何をもって違法と考えるかと言うことについては、いわゆる行為無価値論と結果無価値論の争いがある。詳細についてはこんな雑文でカヴァーできるものではないが、ざっくりいうと、客観的な結果の反価値性を問題とするのが結果無価値論であり、そこに行為の主観性を問題とするのが行為無価値論、といっていい。
学説史的にいうと、團藤重光から大塚仁、福田平へのラインが行為無価値、團藤門下でありながら團藤を強く批判した平野龍一から西田典之、前田雅英へのラインが結果無価値、というところだ。それでは法実務ではどうかというと、これが単純には見えてこない。民事訴訟法の訴訟物論争が、新訴訟物理論の問題意識を取り込みつつ旧訴訟物理論が動かなかった民事実務とは、その点が違う。
いろいろ私がかじった限りでいうと、いわゆる刑法総論講義案、これは裁判所職員の内部教育向けの本であるが(一般にも流通しており、なんでも司法試験受験生もよく読んでるとか)、わかりにくいのだがどうやらベースは大塚説であるらしいことはわかる。ならば團藤=大塚ラインで動いているかといえば、何となくだが違う気もした。そりゃそうで、違法性についての議論がそのまま刑事の判決に反映されることはないのだろう。
しかし、私はあるところでそのヒントになるような言葉に接した。ずいぶん前の話のようだが、ある裁判官曰く、違法性とは悪いということなんだと。これを読んだとき、私は腑に落ちたような気がした。
違法性についての学説は一筋縄ではなく、例えば結果無価値でも一般人基準を取り入れる前田説と純粋客観説とでもいうべき中山研一博士の見解とではひとくくりにするのは難しい。刑法の学習者を混乱させるところだが、要するに裁判実務の違法性論は、素朴なまでの行為無価値論であると言ってよさそうかもしれない。つまり、悪いと考えられる行為だから違法なのだ、と。
何となくだが、これで争いが熾烈な論点に対する判例の理論づけが分かったような気がした。要するに、これは悪いと考えられる行為だから、刑法の構成要件に該当するのだ、という素朴な価値判断があるような気がする。お暇な方は、刑法の判例集片手に検証してみられると良い。
確かに、一般受けは良いのかもしれない。しかし、それでは何をもって「悪い」というのだろうと、私のように人間がひねくれた者は思うのだ。結局ただ「悪い」というだけなら価値判断だし、それこそ前に書いた話と繋がるのだが、ここに「国家権力が望ましいとする」道徳基準が読まれるとすれば、それは「司法」というものの死亡証書になりはしないかと思ってしまう。
まあそれはともかくとして、この考え方は、現代刑事法が超克してきた主観的違法論に近づいてしまいかねないのではないかとさえ思う。もっというと、主観主義的刑事法への接近と言えるかもしれない。確かに客観主義的刑事法は主観主義的刑事法の批判を受けて発展した面もあるのだが。
いや、そこまで言わなくとも、果てして「悪い」ってなんなんだろう。これを突き詰めて考えると、案外難しい。例えば抽象的に「人を殺してはならない」というのは真理だが、それでは「殺す」とはどういうことか。致死効果ありと信じて砂糖を大量摂取させたら?飲ませたのが少々飲んだだけでは死なない薬物だったら?あるいは死ねと念じて丑の刻参りをしたら?
前述の通り、私が懸念するのは「悪い」という素朴な概念に、国家権力にとって都合のいい道徳やら反「秩序」が読み込まれやしないかということだ。そうなってしまったとき、刑事法は国民に対する桎梏へと変わる。NSDAPや1930年代の日本のたどった道が、その証左だ。
やっぱり、国家権力が素朴な概念を持ち出すことは、危険な気がする。やはり刑事実務こそ、何が問題なのかというのをもっと突き詰めて考えてほしいと思うのは、私だけか。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング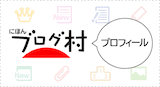

コメント